 「日本は捨てたものじゃない」と信じ経営コンサルティングを行う片山幹雄。日本のメーカーが生き残るための手がかりを経験から示唆する。
「日本は捨てたものじゃない」と信じ経営コンサルティングを行う片山幹雄。日本のメーカーが生き残るための手がかりを経験から示唆する。今年3月に日本電産を退社した片山幹雄(シャープ元社長)は、最近、メーカーを訪問していると、よくこう言われるという。「すごい製品をつくることができました」。自社が開発した技術を品評してほしいと言われるのだ。 片山がかつて「液晶のプリンス」と呼ばれ、世界で戦ってきた経験を考えると、意見を聞きたくなるのは当然だろう。
しかし、片山がその技術を称賛しつつも「これは売れますか。収益は出せますか」と尋ねると、一瞬、間があく。そして「売れます」とは言うが、「もうかります」という答えは返ってこない。「競合はどこですか」と続けると、ほとんどの人が「性能が優れています」と答える。
日本企業の強みはQCDにあるといわれる。Quality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)だ。しかし、片山はその考え方に疑問を呈する。
日本企業については「品質はいいがコストで海外勢に負けた」と説明されることが多い。しかしそれは間違いで、デリバリーで負けているのです。
顕在化している代表例が、液晶、半導体、電池です。
私がシャープの液晶事業本部長だった1990年代末から2000年代初頭のころ、こんなことがありました。他社の液晶事業部の幹部たちが「もう液晶はダメになっていきますね」と悲観して「シャープさんはいいですよね」と言うのです。当時、90年代後半からパソコン市場が一気に拡大して、液晶ディスプレイの需要が高まっていました。世界の名だたるPCメーカーが液晶を買い求めているのに日本の液晶メーカーの供給能力が追いつかない。
「シャープさんはいいですよね」と嘆くのは、当時、シャープが液晶への投資にかじを切っていたからです。 液晶は資本集約型産業で投資が必要です。しかし、日本の総合電機メーカーは多数の事業を抱え込んで展開している。液晶という一事業に大型投資ができる構造にありません。しかも、国内の競合企業の数が多い。国内の多くの液晶メーカーに投資が分散されている状態でした。
Read full article
日本企業については「品質はいいがコストで海外勢に負けた」と説明されることが多い。しかしそれは間違いで、デリバリーで負けているのです。
顕在化している代表例が、液晶、半導体、電池です。
私がシャープの液晶事業本部長だった1990年代末から2000年代初頭のころ、こんなことがありました。他社の液晶事業部の幹部たちが「もう液晶はダメになっていきますね」と悲観して「シャープさんはいいですよね」と言うのです。当時、90年代後半からパソコン市場が一気に拡大して、液晶ディスプレイの需要が高まっていました。世界の名だたるPCメーカーが液晶を買い求めているのに日本の液晶メーカーの供給能力が追いつかない。
「シャープさんはいいですよね」と嘆くのは、当時、シャープが液晶への投資にかじを切っていたからです。 液晶は資本集約型産業で投資が必要です。しかし、日本の総合電機メーカーは多数の事業を抱え込んで展開している。液晶という一事業に大型投資ができる構造にありません。しかも、国内の競合企業の数が多い。国内の多くの液晶メーカーに投資が分散されている状態でした。
Read full article
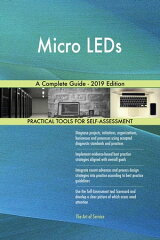
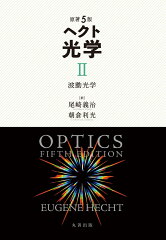














































Comment
コメントする